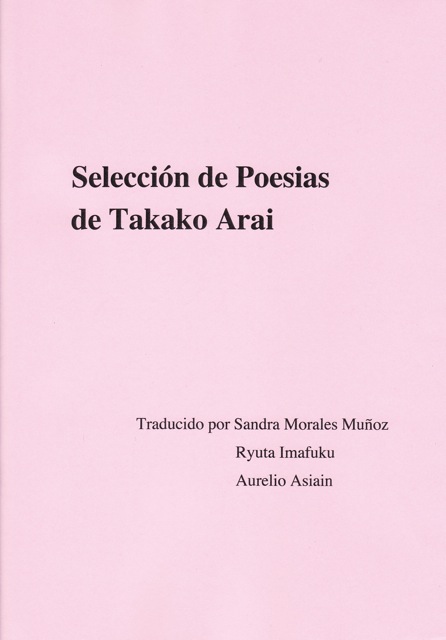編集人:新井高子Webエッセイ
5月のエッセイ
- わたしのアルゼンチン訪問記 ――第十回ブエノスアイレス国際詩祭に参加して
子どもの頃、図鑑好きな兄が言った。「地面の下にはマグマがある。マグマは赤くて熱い。それでも我慢して掘れば、アルゼンチンに出るぞ。そこは日本の反対側だ」。それから毎日、庭の決まった場所に座り込み、わたしは穴を掘った。いや、突き刺して擦っているだけだった。道具は、竹箸ほどの棒っ切れだから。それでも、頭の中には、アルゼンチンという不思議な響きが木霊していたっけ。まだ四才、そのときのわたしは。
それから、四十年以上経ったこの四月、ようやくかの地に到着した。空路でも二十数時間かかる長旅。ボルヘスやコルタサルを生んだそこは、文学とカフェを誇りにする土地柄で、ブエノスアイレス国際詩祭という大きな詩祭を毎年開催している。日本詩人クラブ会長の細野豊さんを通じ、詩祭ディレクター、Graciela Aráoz(グラシエラ・アラオス)さんから招待状をいただいたのは昨年十二月のこと。出演者自身で準備するよう言われたスペイン語訳詩が課題となったが、幸い、今福龍太さん、アウレリオ・アシアインさん、野谷文昭さんの紹介のサンドラ・モラーレスさんによる、九篇もの訳詩が手もとに届く。嬉しさの余り、冊子にした小詩集は『Selección de Poesias de Takako Arai』。
この小冊子が何よりの励ましになった旅だった。二〇一五年のブエノスアイレス国際詩祭、第十回目の記念祭には、アルゼンチン国内各地から十七名、国外から二十三名、合計四十名もの詩人が競演した。国外の参加者もメキシコ、キューバ、チリ、パラグアイなど、スペイン語圏の詩人が非情に多い。英語だって日常会話程度だが、スペイン語はさらさらできないわたし……。この訳詩集が作品の内容を伝えてくれたのはもちろんだが、その前に、それを手渡そうとする振る舞いも大事だった。おかげで、多くの人と片言ながら直にことばが交わせ、しばし笑い、関係を結ぶきっかけができたのだから。詩祭での遭遇をわたしなりの「出会い」に伸ばせた気がしている。
北米ばかりからアメリカを感じてきたわたしにとって、スペイン語のアメリカがこれほど広大だと実感できたのは、逆立ちして地球を眺めた新鮮さ。そして子どもの頃、兄が「反対側」と言った通り、たしかにアルゼンチンは、日本、少なくともいまの東京とはぜんぜん違う思考回路で動いていた。街路樹のプラタナスが黄葉しはじめた初秋の南半球、八日間にわたる華やかな詩の祭典を振り返り、もっとも懐かしく、印象深く思い返すのは、そんな対照的な人間たち。一言でいえば、システムよりも、「余白」で勝負する人の輝き。その場に集った者たちが偶然や巡り合わせを味方に付けながら、手探りの瞬発力で状況を作り上げる面白さ。
まず、それにおぼろげに気付いたのは、自己紹介を兼ねながら、出演者それぞれが一篇ずつ詩を読む会でのこと。運営アシスタントで英語が堪能なJimena de la Barra(ヒメーナ)さんとは、渡航前から頻繁にメールでやりとりしてきたが、その中で確認したことの一つが「わたしの朗読は日本語でいいか」。答えは「タカコは日本語。翻訳は、スペイン語の詩人が朗読する」。
それが、会場で、ヒメーナはにこやかにこちらに近付き、「ハーイ、タカコ、あなたのスペイン語はだれが読むの?」(かの地で、詩人たちは敬称なしで呼び合っていたので、以下省略)。段取りとは主催者側が細部まで詰めるものと思い込んでいた東京流のわたしは、メールの文面からその人選はしてあるのだろうと無意識で思っていた。でも、ここでの論理は、本人が頼めばスペイン語の詩人が朗読する、なのだ。アリャッと、戸惑うわたし。ありがたいことに、小詩集を渡しつついっしょに談笑していた傍らの詩人、コロンビアから来たRamón Cote Rabaibarが「じゃあ、僕が読もう。何ページの詩?」と名乗りでてくれ、ほっとする。
主催者は、詩祭の中のたくさんのイベント、その日時や場所を決め、すでに広く宣伝してあるけれども、各詩人の枠を仕切るのは、本人自身。外国から到着したばかりであっても、じぶんの裁量や交渉力でその「余白」は切り盛りしないといけない。アルゼンチンが誇る伝統的なカフェでの朗読会、ブエノスアイレス国際ブックフェアでの朗読会、閉会式での朗読と、これからある三つの舞台を前にして、にわかに面白くなってきました。
じつは、おかげで、スペイン語がわからなくても、ほかの出演詩人の朗読を興味津々で聞けるようになったのだ。町工場のざわめきやことば遊びに満ちた拙作の内容は難しい。それに耳傾ける聴衆のためにも、できるだけベストな人に頼みたい。そこで、どんな声や読み方がわたしの詩、その日に読むつもりの訳詩に向くか、主体的に選び始めているじぶんに気付く。「しごと」ができたのだ、オーディエンスでいるときも。たぶん、ほかの詩人も聴衆も、なにかを探りながら座っていたんじゃないか……。うまく言えないのだが、そんな能動的な気配、敏捷な頭とからだの「ノリ」がわたしにも移ってきたのです。
スアレス通りにある「La Flor de Barracas(ラ・フロール・デ・バラカス)」という素敵なカフェで行われる会では、コミカルな詩と織物工場の詩を読もうと思っていたので、パナマから来たLucy Cristina Chau(ルーシー)にお願いする。白人とアフリカ系の混血のようにも、フィリピンやポリネシアと繋がりがあるようにも見える彼女は、一九七〇年生まれで出演者の中では若手。その自作朗読を聞くと、落ち着いた音域で、軽やかにも濃やかにも、声の細部まで配慮を行き届かせている。「Wheels」という長篇を読む閉会式は、リオ・ネグロ州に住むアルゼンチンの詩人、Graciela Cros(グラシエラ・クロス、一九四五年生)にお願いする。彼女の朗読には、どっしりした語りの力、意味を他者に伝える最後の「ひと押し」がある。それは、語りながら、音域を徐々に深めていくことができるからだろう。
二人とも「喜んで!」と快諾してくれた。じつは日本に帰って、略歴一覧をゆっくり眺めてわかったのだが、ルーシーもグラシエラ・クロスも、ナレーションの仕事をしている詩人だった。期せずして、詩を耳から伝える専門家に頼んでいたのだ。どおりで素晴らしかったわけだと納得すると同時に、声の力量の違いは明瞭だと悟り、我が身に照らし恐くもなる。
「ドラマ」は、国際ブックフェアでおこるのですが、それはおいおい。
「ラ・フロール・デ・バラカス」での会が跳ねた後には、出演者たちといっしょに、「La Poesía(ラ・ポエジーア)」という別のカフェで行われる朗読会に向かった。
ブエノスアイレスでは、歴史的な建築と文化を持ったカフェが町の指定を受けている。ユネスコの文化遺産に登録する動きもあるそうだが、詩人や小説家、画家や音楽家がそこにたむろし、新しい芸術を作り上げるトポスになったのは、言うまでもない。そこで、詩祭ディレクター、グラシエラ・アラオスは、詩と町と歴史を結ぶコンセプトで、伝統ある瀟酒なカフェで連続的な朗読会を組んでいる。二日間に十ヶ所、リレー式で。わたしたちの会もそうだったが、どこに出掛けても満席なのには驚いた。主催者が相当な努力をしていること、今年十回目の詩祭が土地に根付いていること、詩に熱心な聴衆があることを実感する。振り返れば、どの本屋に寄っても、詩集の棚は堂々たるスペースだった。
「ラ・ポエジーア」でのわたしの目当ては、イラク生まれでイスラエル在住の詩人、Ronny Someck(ロニー、一九五一年生)の朗読を聞くこと。人は短時間で関係の網を作っていく生き物。詩祭が始まって二日もすると、ロニーは、スペイン語圏以外から来た詩人の要になっていた。偉そうな素振りは全くないのだが、彼がいると、穏やかな風格によって、すっと場が落ち着く。そこにいる雑多な人間の「気」を自然に飲み込む懐の深さに、秘めた怪物性を感じた。朗読には、引き裂かれたロニーの自分史がうつって見えた。英語の詩集の一つは『The Fire Stays in Red: Poems』(University of Wisconsin Press, 2002)。
キューバの詩人、Roberto Manzano Díaz(ロベルト、一九四九年生まれ)も、忘れられない。ブエノスアイレス在住者以外は、みな同じホテル(ガルシア・ロルカがかつて定宿にしていた、Castelar Hotel)に泊まっていた。わたしも含め、ほとんどの詩人は、催しがない時間帯は、美術館や観光スポットへ出掛けたり、部屋で書き物をしたりしていたが、彼はたいていロビーにゆったり腰掛けている。そして、ホテルに行き帰りする詩人を待ち受け、しばし談笑するのだ。つまり、わたしたちが小鳥なら、ロベルトは巣のよう。駆け回らなくても世界は知ることができるという達観に見えた。突き抜けた人なのだろう。朗読は、気骨に溢れていた。スペイン語詩のアンソロジーとして『El impulso inagotable: Selección de obra publicada』(CreateSpace, 2013)。
アラビア語の寛大さを声に乗せるエジプトのAhmad Al-Shahawy(一九六〇年生)、皮肉と愛敬が入り交じった知性、デンマークのNiels Hav(一九四九年生)、詩祭後まもなくPushcart Prizeの受賞ニュースが入ったカナダのNicole Brossard(一九四三年生)、ビジュアルポエトリーを発展させるポルトガルのFernando Aguitar(一九五六年生)、野太さと優しさが同居するパラグアイのRamón L. “Moncho” Azuaga(一九五二年生)、詩と朗唱を繋げる南アフリカのGcina Mhlope(一九五八年生)、ブエノスアイレス在住で韓国語で詩を書き続けるJo Mi-hee(一九六一年生)など、多彩な出演者を書き出すと止まらない。
螺旋を描くような独特の声、思索の響きがいまもくっきり耳に残る詩人、アルゼンチン文芸家協会代表でもあるVíctor Redondo(ヴィクトル、一九五三年生)は、かつては駅舎として使われていたという協会のアール・デコ調の建物で昼食会を開いてくれた。ボルへス、コルタサル、女性作家のヴィクトリア・オカンポなど、ブエノスアイレスが生んだ偉大な文学者の肖像に囲まれた部屋。彼らとも食事をしている気持ちになりながら、国際詩祭を粘り強く継続させているのは、この町の文学への敬愛なのだ。
さて、「ラ・ポエジーア」での朗読の後は飲み会になった(カフェと書いたが酒も飲めるので、つまりカフェバー)。詩祭のほとんどの夜を締めくくるのは、酒宴。ヒメーナ、もうひとりのアシスタント、Noelia Andia(ノエリア)とわいわい騒ぎながら、その席で、ブエノスアイレス在住の詩人、Ricardo Rojas Ayrala(リカルド、一九六八年生)に、国際ブックフェアでの訳詩朗読をお願いする。フェアでは、ことば遊びをパンチにした「ガラパゴス」を含む震災や原発事故を踏まえた詩を読むつもりだったので、リカルドならケレン味のあるリズムにも合わせてくれるだろうと踏んだのだ。彼の自作朗読は、音遊びをふんだんに入れ、身ぶり手振りも愉快だった。
ビールを何本も飲み、酔っぱらったわたしたち。小柄で小太りのリカルドはすでに赤ら顔になっていたが、わたしの申し出に胸をどんと叩き、「まかしとけ!」。
翌々日五時半ごろ、ブックフェアの会場にホテルからのバスでわたしは到着。会にはまだ間がある。四十一回目を数える、ブエノスアイレス国際ブックフェアは、大型パビリオンがいくつも並び、アルゼンチン国内の出版社だけでなく、世界中から店が並ぶ大規模フェア(日本のブースもあった)。そこかしこで、作家、詩人、批評家のトークや朗読会が行われている。もちろん、お客さんもわさわさいる。
わたしたちの朗読会場、「Sala Juan Rulfo」の客席でぼんやりしていると、コルドバ州から来たアルゼンチンの詩人、Pablo Anadón(パブロ、一九六三年生)が話しかけてくれる。パブロは大活躍の詩人だった。自作朗読のほか、イタリアの詩人、Mirella Muiàとインターネット映像で繋がった公開対話も引き受けていた。コルドバで刊行されている『Fénix』という詩と批評の雑誌の編集者でもある彼は、この詩祭きっての知性。細身の長身で、端正な雰囲気だが、なにかに熱中し出すと、目がまん丸になってキュート。「ラ・フロール・デ・バラカス」でのわたしの朗読も聞きにきてくれた。
「タカコ、おとといの会に、ブエノスアイレスの素晴らしい詩の雑誌『Hablar de poesía』の編集者も来ていたよ。それで、タカコの詩を掲載したいと言っている。今日、その件で話すために、日本語ができる娘さんとまた来るそうだ」。拙い英語の耳を疑う素敵な申し出に、呆然とするわたし。そして、今日の朗読は神経を研ぎすまし、絶対集中しようと、柄にもなく肩に力が入った。
が、であればこそ、そうは問屋が卸さないのが「アルゼンチン」(笑)。ご当地ならではの「余白」の時間を身を持って体験することになりました。以下、実況中継風に。
ところで、気になるのは、もうじき開始だというのに、リカルドがいないこと。でも、出番の七時までは一時間あるのでそのうち来るだろうと、一グループ目の詩人たちの朗読に耳を傾ける(朗読は三人が一グループで行ない、わたしは三グループ目)。それが終わると、アシスタントのヒメーナがツカツカと……。
「タカコ、あなたはいま、ブックフェアの事務室に行って、ギャラをもらわなければならない」。どうして、いまなの? 大一番を前に集中したく、後にしてほしいと抵抗するが、事務室が閉まってしまうのだと、ヒメーナはわたしを引っ張っていく。出演料は欲しいが、しぶしぶ付いていきながら「リカルドがまだ来ていない」とこぼす。「大丈夫。絶対来る」とヒメーナ。心配そうなわたしを見て、いっしょに向かうアルゼンチンの詩人、Beatriz Vignoli(ベアトリス)は「もしものときは、あたしが読むよ」となだめてくれる。
しかし、なんと広大な敷地か。三つも四つも離れたパビリオンの中だったのだ、その事務室は。着いたときはもう出番の十分前。「間に合わないんじゃないか」と案ずると、ヒメーナは「大丈夫。アルゼンチンではすべてのことが遅れる」。そうであった、確かに。一グループ目が終わったとき、すでに十分近く押していた。が、控え室で待たされた数分間、なんと長かったことか。戻りたくて仕方がなかったが、この距離では迷子になること、間違いない。
ようやく案内されると、長身のその男は、室長というよりあたかもマジシャン。こちらの焦りなど意に介さず、タロットカードのごとく勿体ぶって百ペソ紙幣を数え、ウィンクしながら得意げに差し出す。瞬時に換算すればほぼ二万円、たった十数分の朗読に。これは魔法か、インフレか。出番の心配をよそに、ほくほくするじぶんが情けない。
が、時計を見れば七時を回った。間に合うかどうかも自己責任なのに、なぜ現場を離れたか、オマエは朗読のために遥々来たんじゃないのか……、大げさな自責の念がおつむを巡る。さすがのヒメーナにも気持ちが移ったようで、「近道で行こう」。そして案の定、道に迷う。そうなのだ、こういうとき、人はこうなるものなのだ。もういい。わたしがいなければ、つぎの機転を利かすのもアルゼンチン。なるようになれ。腹を括ると迷子から抜け出せるのも、世の常ですね。
競歩のごとくパビリオンの床を蹴り、会場に突進する。猛進する。司会のグラシエラ・アラオスが、三グループ目をコールする声が聞こえる。間に合った、アルゼンチンではすべてが遅れて助かった(笑)、と安堵。
が、リカルドがいない、会場中を見回しても。なら、ベアトリスは? 出番が終わった彼女は、途中でゆっくり歩き出し、たどり着いていない。グラシエラは「タカーコ、タカーコ」と呼んでいる。「ハーイ」と振り返りつつ、瞬時にパブロに頼む。こんな臨機応変な英語力、火事場の馬鹿力としか思えない。
そして、息を切らせて登壇。集中して臨もうと思った目論見はアワと消えたが、そんなの、どうだっていい。呼吸を沈めよう、ともかく。ありがたいことに三人中のラストなので、最初の詩人の紹介の間、わたしは詩の順番を傍らのパブロに耳打ち。スマートな彼は、意識を澄ませて下読みを始める。いきなり頼まれた方も大変だ……。
そこで、パッと開いた、正面の扉が。ヒメーナが誰かと話している。ひょっこら入ってきたのは、あのリカルド! 真ん中の通路を五、六歩進む。止まる。両手を投げ出し、いかにもすまなそうな顔。ひしゃげた男が、会場の外の光を背中に浴びて、一心にフリーズしている。この上なく儚い瞳をわたしに向けて。「Come Oooon!」、心で叫んだ。
精読中のパブロに、向こうを指さす。ニヤッと了解する彼。そして、「交替するから、上がってきて」と、小さな身ぶりでフリーズ男に伝えると、二人は入れ替わる。ごくごく平然と。「ごめんよ。車が混んでたんだ」、小声で謝ってくれたけれども。
訳詩朗読が、期待以上に、ケレン味たっぷり、サービス満点になったことは言うまでもない。日本語テキストの説明までしてくれた。わたしも吹っ切れて、ふだんにないドスが響くのにじぶんで驚く。密室的な集中力とは対極的な、どさくさの度胸、居直りの瞬発力のおかげだろう。朗読のあと、「Hablar de poesía」の編集者、Ricardo H. Herreraは、娘のJulietaと駆け寄ってくれ、「思った以上に、あなたは力強い詩人だね」。
それは、アルゼンチンが引き出してくれたもの。これまでわたしは「力強い」と形容された覚えがない。体格もキャシャな方だ。はるかな異国、初めてお呼びがかかった国際詩祭で、ともかく自力で立ち回り、綱渡りでも状況を捕まえられた。こつこつ予定をこなしたのとは違う、一種、「神業」的な達成感。この町がそれをくれたのだ。
「いいかげん」とは違うのだと思う。じつは、詩祭だけでなく、地下鉄に乗るときも、美術館を訪れたときも、制度らしきものは、途中までしか働いていなかった。つまり、するべきことをしていないのではない。予定やコントロールは初めから途中までなのだ。最終ポイントは本質的にいつも「空白」。まっさらな現場を、運だめししながら応酬するのが道理なのだ。
その空白こそ、人とことばを鍛えるのだろう。人びとが、臨機応変に挑む能動的な姿は、喩えるならピューマかジャガーか……。敏捷に飛び交って、決着点を即時的に創り出す。システムに守られた日本では、最初から最後まで制御されすぎて、頭とからだの「筋力」、意欲や想像力が甘やかされていたんじゃないか、わたしは……。ほんのつかの間だけれども、南米のピューマの中に紛れ込み、めっぽう爽快だった。
その文学にマジック・リアリズムが生まれたのは、日々の暮らしの中に奇跡的な神業がふんだんにあることと無縁でないだろう。ここでは世の中は「迷宮」だと感覚するほうが、自然だ。ほんの十日間の旅行だけれども、つくづく思う。人びとが空白で錯綜すれば、それはおのずと眼前に立ち上がる。実際に迷子になった、あのパビリオンはわたしにとって迷宮と呼ぶほかない。いつ、なにが飛び出してくるか、どこに落とし穴があるか、計り知れない……。そして、ある意味、世の中というものの本質、その野性味を、隠していないのだと思う。迷宮とは都市の荒野か。この国の人たちは、そんな裸の状態が好きだから、制度という衣服の過剰を冷笑し、プイと、拒んでいるのではなかろうか。
いまも目を閉じると、浮かんでくる、両手を投げ出したリカルドの、崩れたシルエットが。思い描けば描くほど、神々しく見える。まるで花道の道化役者のように滑稽で、それでいて無性に哀愁を掻き立てられる。荒野にひとりぼっちで佇む人間の頼りなさ、寄る辺なさ、それを受け入れざるを得ない無力が、あの瞬間、煌々と、その肉体に凝縮されていた気がする。ピューマの裏面だろう。
それは、駆けずり回って探し当てた、わたしのアルゼンチンの「ポエジー」である。
* 第十回ブエノスアイレス国際詩祭(2015. 4. 19〜26)のウェブサイト
http://festivalpoesiabsas.com.ar/wordpress/
https://www.facebook.com/festivalpoesiaba
ブログラム、出演者一覧、記録映像、写真などを掲載。
* 新井高子スペイン語訳小詩集
『Selección de Poesias de Takako Arai』
Traducido por Sandra Morales Muñoz, Ryuta Imafuku, Aurelio Asiain
* 都市の荒野と言えば、五月広場に面した大聖堂も忘れがたい。大勢の信者がひしめく中、厳粛に行われている日曜のミサ。その聖歌に驚いた。伴奏はオルガンではなく、ハモニカ、ギター、そして太鼓など。歌声はほぼ地声。美しいステンドグラスの教会の内部に「荒野」か、と想った。
* 事務室との往復の間、ヒメーナは何度も携帯電話を覗いていた。会場の進行の様子を、もうひとりのアシスタント、ノエリアに確認していたのだろう。メール交信、わたしへの配慮も、ピューマのように飛び交っていたのだ。
末筆ながら、盛大な詩祭を運営したグラシエラ・アラオス、ヴィクトル、ヒメーナ、ノエリア……に心から感謝します。
参加にあたって、国際交流基金の助成を得た。

Copyright © Mi'Te press. All rights reserved.
Designed by MOGRA DESIGN