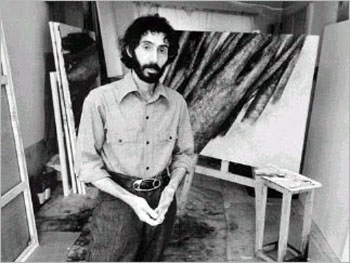編集人:新井高子Webエッセイ
6月のエッセイ
- 「ひなげしがある限り、生きなければならない」――イランの詩の物語(4)
友だちのうちはどこ?
「友だちのうちはどこ?」というイランの映画をご存知だろうか。中東の国イランの映画が広く日本でも上映されるようになったきっかけとなった作品、そして、アッバース・キアロスタミ監督の一連の作品のうち、最初に日本に上陸した映画である。
吸い込まれそうな黒い瞳をした、あどけない少年アフマドが、宿題ノートを届けるため、友だちの家を探して歩く物語だ。同級生のモハンマド=レザーは、昨日も今日も、宿題を忘れて先生にこっぴどく叱られていた。それなのに、主人公の少年は、間違えてモハンマド=レザーの宿題ノートを家に持ち帰ってしまったのだ。草原の広がるジグザグの坂道を駆け上り、山あいにひしめく家々を、アフマドは訪ねて歩く、「友だちのうちはどこ?」と。
そして、この映画にインスピレーションを与えたのが、イランの現代詩人ソフラーブ・セペフリー(1928-80)の詩「住所」であった。
暁の頃、馬に乗った男が問うた
空は静止し
旅人は口に銜えた光の枝を砂の暗闇に委ね
そして白楊の木を指差して言った
「あの木の手前
神の眠りよりも翠色をした小路がある
そこでは 愛が誠実の羽くらい蒼い
成熟の向こうから現れたその小路の終わりまで行き
そして孤独の花の方を向いて
花のところまで二歩のところ
地上の神話が永久に噴き出ているところに居てごらん
すると透明な畏れがお前を取り囲み
誠実に流れる空間の中で さらさらという音が聞こえるだろう
高い松の木にのぼって光の巣から
ひな鳥を捕まえている子供が居るから
その子に尋ねてごらん
友だちのうちはどこ、と」
鈴木珠里(訳)「住所」*
新・神秘主義の世界
この不思議な詩から何を感じ取られるだろうか。無論、この問いに正解などないのだが、イランの読者がセペフリーの詩に重ね合わせるもののひとつとして、イスラーム神秘主義の世界がある。
イスラーム神秘主義とは、神への熱烈な思慕を原動力とした禁欲的求道精神であり、「我」の消滅と神との「合一」を最終目標とする。神への熱愛を主題とする神秘主義文学は、(とくにイランにおいて)現世の愛を、神への愛の象徴とする独自の表現体系を発展させた。セペフリーの詩には激しい熱情は見られないが、光に溢れた精神世界への希求ゆえに、彼の詩は「新・神秘主義」と名付けられた。神秘主義において、神へと至る道程は、ときに「旅」に喩えられ、「旅人」である修行者は、七つの階梯を経て、合一の境地に達するとされている。作品『住所』に示される道標と、「dust(友、恋しい人)の家はどこ?」の問いは、神秘道の階梯にもなぞらえられる。
「緑」の詩人セペフリー
ソフラーブ・セペフリーは、一九二八年にイラン中央部の小都市カーシャーンに生まれた。カーシャーンは薔薇の産地として名高い。花を摘み取り、薔薇水と呼ばれる調味香料や香水を産出するのである。収穫期に訪れると、花を摘んで加工する早朝には、街中が薔薇の香りに包まれると言う。
セペフリーは、生涯の大半をこの薔薇の街カーシャーンで過ごした。残された彼の写真を見ると、線の細い、嫋々とした面差しで、なにやら森の妖精のようだ。彼の代表的な詩集が『緑のひろがり』(1967)である。彼の詩のすべては、「緑」につながっている。「緑」とは、文字通り、木々と草花であり、これらが湛える水であり、注がれる光である。そして、これら全てと一体となった「わたし」が、その傍らにたたずむ。
雲もなく
風もなく
わたしは腰をかける 池のほとりに、
魚たちの遊泳、明るさ、わたし、花、水
生きることの 一房の清らかさ
* * *
救いは すぐそこにある、庭の花々の間
* * *
わたしは道を見いだす 暗黒の世界で、わたしは 灯りに満ちている
わたしは満ちている 光に、砂粒に
わたしは満ちている 木に、枝々に
わたしは満ちている 水面に映る 木の葉の陰に
わたしの心は 何と孤独なのだろう
「明るさ、わたし、花、水」
セペフリーは、詩作の初期の段階から、東洋思想に大きな関心を寄せていた。自己と世界の対比と事象の対象化を是とする西洋哲学に対して、東洋思想は己と世界の「調和」と「一体性」とを志向する----という彼の認識と憧憬は、彼の「緑」の世界を創り出している要素のひとつである。セペフリーは、実際に、数回に渡りインド、パキスタンへと旅しており、一九六〇年には、彫刻を学ぶために日本を訪れた。帰国後、彼は「日本の戯曲」として、世阿弥の能曲『老松』と『敦盛』を相次いでペルシア語に翻訳している。そして、この後しばらくして書き残した詩のひとつが、次の「終焉まで在り続けるもの」である。
今宵
奇妙な夢の扉が
言葉に向かって
開くだろう。
風は 何かをささやくだろう。
林檎は 落下し、
大地を描き出すことばの上を
夜にひそむ 故郷の在処まで転がっていくだろう。
夢想の天蓋は 崩れ落ちるだろう。
眼は
飴色の哀しげな理知を見るだろう。
暗黒の道の途中で水の語らう畔は
輝くだろう、
鏡の内奥は 知るだろう。
***
夜の底で、一匹の虫が
孤独という瑞々しい定めを
生きるだろう。
朝という言葉の内で
朝は 訪れるだろう。
「終焉まで在り続けるもの」
1960〜70年代のイランでは、政治活動への参与が文学の至上命題とされ、詩人には詩を通じて大衆を導く義務があるとされた。しかし、セペフリーは一貫して、これを拒み続け、詩人として(朗唱会の)聴衆の前に姿を現すことさえ拒否していた。彼の姿勢は、同時代の文学者たちの中でも、極めて異例と言わねばならない。一方、画家としてのセペフリーは、パリを初めとするヨーロッパ各都市で、幾度となく個展を開催し、精力的な活動を展開している。「隠遁の詩人」と称されたセペフリーの詩人としての生き方は、彼の強固な意志に裏打ちされたものであったのかもしれない。
僕は人々を見た。
無数の街を見た。
平原を、山々を見た。
水を見た、地を見た。
* * *
光の中に獣を、闇の中に獣を見た。
光の中にヒトを、闇の中にヒトを見た。
「水の足音」
わたしは今日、何と「緑」なのだろう!
* * *
優しさがある、林檎がある、信じる心がある
そう
ひなげしがあるかぎり、生きなければならない。
「ゴレスターネ村で」
* セペフリー「住所」は、イラン文学研究者・鈴木珠里さんの訳を以下より引用。
鈴木珠里「映像になった言葉たち〜イラン映画と詩の蜜月〜」『イランを知るための六十五章』(岡田恵美子・北原圭一・鈴木珠里編)
明石書店 2004 (鈴木珠里ほか編『現代イラン詩集』土曜美術社出版販売, 2009にも再録)
** その他の詩篇は、いずれも前田君江訳(上記『現代イラン詩集』より)
*** 本エッセイは、詩誌『ミて』73号(2005/5)に掲載のセペフリー訳詩と解説を加筆修正したものです。
Copyright © Mi'Te press. All rights reserved.
Designed by MOGRA DESIGN