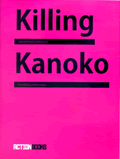編集人:新井高子書評
伊藤さんのおまじない―d-labo主催「実作者と翻訳者」イベント評+伊藤比呂美『読み解き「般若心経」』書評
(伊藤比呂美『読み解き「般若心経」』朝日新聞出版、2010)
( Killing Kanoko by Hiromi Ito (translated by Jeffrey Angles), Action Books, 2009)
藤井一乃(編集者)
2010年4月1日。六本木・東京ミッドタウンにある、スルガ銀行が運営するコミュニケーションスペースd-laboにて、伊藤比呂美氏とジェフリー・アングルス氏による公開トークと朗読「She Who Creates and He Who Translates 実作者と翻訳者 合体することば 越境する身体」が行われた。アングルス氏は、現在、西ミシガン大学で日本文学を研究、今年9月まで国際日本文化研究センターに招聘されている。これまで数多くの翻訳を手掛け、昨年、多田智満子訳詩集でドナルド・キーン日本研究センターより日米友好基金日本文学翻訳賞を受賞した。今回のイベントは、昨年末、アングルス氏による伊藤氏の翻訳詩集『Killing Kanoko』がアメリカのAction Booksという出版社から刊行されたのを機に、新井高子氏らの尽力によって実現した。当日は、実作者と翻訳者、それぞれの立場から『Killing Kanoko』をめぐるエピソードと詩の朗読を中心に、他言語で書くことの難しさと喜び、自らのセクシャリティについての話題にも踏み込んで、笑いの多い刺激的な時間となった。
伊藤さんの話が聴けるのは何よりもうれしい。これまで「伊藤さんが日本にいてくれたら…」と思っていた、その飢えの気持ちがうるおう。というのも、私がものごころついたときには、伊藤さんはすでに熊本に、私が、この世に詩というものがある、と気がついたときには、アメリカに拠点を移されていたと記憶する。いまは、カリフォルニアと熊本の往復の途中で、ときどき東京にも立ち寄られて、こうして朗読や詩の話を聞くことができる。十数年ぶりに詩を再開、「現代詩手帖」に「河原荒草」の連載がはじまり、2005年にそれが一冊にまとまったとき、その朗読を何度か聴いた。その喜びも記憶に新しい。
伊藤氏を中心に活動する「熊本文学隊」の様子も、こちらに伝わってくる。今年3月には、北米先住民の口承詩の研究で知られるアメリカの民俗学者であり、詩人のジェローム・ローゼンバーグ氏が来日。「くまもと連詩」として、伊藤氏、谷川俊太郎氏、四元康祐氏、覚和歌子氏、通訳としてアングルス氏が参加して大規模な連詩が行われた。このローゼンバーグ氏の仕事と、それを日本に紹介した金関寿夫氏の仕事が、伊藤氏がアメリカにわたる大きなきっかけとなったという(ローゼンバーグ氏とは、アメリカでもすぐ近くに住んでいるそうだ)。アメリカの口承詩がかつてのビート・ジェネレーションに与えた影響、ビートが日本の現代詩に与えた影響を考えるとき、その有形無形の恩恵を思い、それがいまある私たちの時間空間に脈々と繫がっているということに、改めてこの場の貴重さを感じる。
この日の朗読では、伊藤氏の作品が、実作者と翻訳者との呼吸のあった掛け合いで、いままで活字で読んでいたのとは違う表情をもってたちあがってきた。とくに、「意味の虐待(The Maltreatment of Meaning)」という作品。
わたしは血まみれの意味はみじめでうれしい
I am happy meaning covered in blood is miserable
あなたは血まみれの意味はみじめでうれしい
You are happy meaning covered in blood is miserable
わたしたちは血まみれの意味はみじめでうれしい
We are happy meaning covered in blood is miserable
この詩は、もともと上野千鶴子氏との共著『のろとさにわ』に収められた作品で、「あなたはニホン語が話せますか」といったシンプルな構文が、「わたしは意味を剥がしとりたい」という詩行をあいだにはさみながら、最後には「血まみれのそれの意味の血まみれのみじめさだ、それうれしい」という一行で終わる。今回の朗読では、伊藤氏が日本語で一文を読み、それに続いてアングルス氏が英語で読むというかたちで、ときに即興的に朗読が進み、行を追うごとに言葉が少しずつずれて意味も文法も壊れていき、コミュニケーションの難しさ、危うさを端的に表現する。日本語だけで見てもことばが壊れていく様子が伝わる刺激的な作品だが、そこに英語が加わることによって、さらに重層的なことばの層、ズレが起こるスリリングな体験を味わう。「翻訳は必ずしもその原文の色あせた写しではない」、翻訳されることによって「オリジナルから独立してよみがえることがある」というアングルス氏の言葉を体現するような朗読でもあった。
また、詩誌「ミて」にはじめて掲載された「河原の婆」は、伊藤氏一人での朗読。
頭の大きな青い茎が 何百本も たおれて そして起きあがり
葛の葉が その上を這いまわり
蔓の先を持ち上げて 入りこめる膣を待つ
その情欲の強さといったら ありません
そんなふうに わたしも 葛と つがいました
ひいる ひいる ひいる ひいる
風が吹いた
(絶対あんな音ではないのだけはたしかだ)
空の一辺で
(絶対あんな音ではないのだけはたしかだ)
雨雲がぎらぎら光った(「河原の婆」より)
植物との性交渉、交歓が自在に描かれているように受け取れるのだが、性の表現なのに、けしていやらしい感じにならず、その清潔さが心地よい。今回の詩集のタイトルにもなった「カノコ殺し(Killing Kanoko)」(『テリトリー論2』1985年所収)は、過剰な性描写のなかに猥雑さと聖性の両方を感じさせつつ、既存の母性神話を解体する伊藤氏の代表作だが、この詩が発表された当時の時代背景、その後の時代に与えたインパクトを考えるとき、現代における「河原の婆」に通じるものが見えてくる。性のとらえ方は時代とともに刻々と変化するが、つねに既存のイメージや枠組をずらしながら描かれる伊藤氏の作品に改めて驚かされた。
*
伊藤さんの朗読は、ひとを助ける。伊藤さんの声を聴くとき、いつもそんな印象を持つ。なんてひとを救う声だろう、伊藤さんの声は、いったいどこから出てくるんだろう。幼い子どものようであり、艶のある女のひとのそれでもあり、おばあさんのようでもある。その声を聴いていると、女たちがこれまで通ってきた道、苦労だとか、喜びだとか、悲しみだとか、そういうものすべて、女ひとりが経験するかもしれないあらゆることが、目の前に広がるように感じられる。伊藤さんの通ってきた道でありながら、匿名の女たち大勢の通ってきた道。「女」という言葉を無自覚に使ってはいけないかもしれない。それでも、伊藤さんの声に、女たちがこれまで経験してきたこと、これから経験するであろうこと、それらが予言的に含まれているように感じられる。medium、「霊媒」である、と伊藤さんは語られた。海千山千ということばは、ふつういい意味で使われないけれども、「女」として生きていくことは、どこかそういうものになっていくことで、途方に暮れることばかりが増えていく。いい歳で、結婚していなくて、途方に暮れる。結婚していて、子どもがいて、それでも途方に暮れる。伊藤さんが経験した人生の苦楽を前に、私などが経験することは、その手前で立ち往生しているようなものだけれど、そんないろんな局面に立つ女たちにとって伊藤さんは道を指し示す存在だ。
その「女たち」にはあてはまらないアングルス氏が伊藤氏の作品に惹かれる理由を、「(自分は)ゲイの男性として自分の立場から性の意義を考えているので、性を面白い角度から見たり、ジェンダーの神話を脱構築したりする作品に惹かれる」と語る。彼がこの詩集の翻訳で試みたのは、男性と女性、アメリカと日本という境界を越境すること、その大きな隔たりへの賭けであり、問いかけなのだろう。そこに伊藤氏の作品の読み、あるいは、かつて「女性詩」として投じられた課題に対する、未知の、新たな可能性と方向性が広がるように思う。
仕事、恋愛、家族、親の介護、老い、その先にある死。これまでの女性たちが当たり前のように経験してきたことを前にして『読み解き「般若心経」』は、切ない一冊だ。伊藤さんがご両親をよく看取りたいという思いから語り出されたお経、ひとが生きて、老いて、そして死んでゆくこと、その先にあるお経である。母の死、友人の死、かつての舅の死、友人の飼っていた犬の死…とても具体的な死を凝っと見つめる伊藤さんの切実さが、彼女の朗読がそうであるように、匿名の、普遍的な感情として伝わる。以前、現代語訳に翻訳された樋口一葉の「にごりえ」にも魅了されたが、こんどの「般若心経」も、伊藤さんの「翻訳」を通して、おそらくオリジナルにつきまとうであろう仏教の複雑な文脈を超えて私たちに届く。
「ある」は「ない」に ことならない。
「ない」は「ある」に ことならない。
「ある」と 思っているものは じつは 「ない」のである。
「ない」と 思えば それは 「ある」に つながるのである。(新訳「般若心経」より)
ふだんは男性に読まれて聴くことの多いお経が、老女のような、幼女のような声で語られる。誰でもあり、誰でもない声。伊藤さんがこの「般若心経」で超えようとしたのも、はかりしれない隔たりの飛躍、たとえば、男性と女性であり、過去と現在、生と死の境界なのかもしれない。
これは つよい まじないである。
これは つよくて あきらかに きく まじないである。
(…)
ぎゃーてい。
ぎゃーてい。
はーらー ぎゃてーい。
はらそう ぎゃーてい。
ぼーじー そわか。(同上)
伊藤さんの声が私たちに届く。日々、迷い、泡立つこころがしずまる。それは、本当によく効くおまじない、何よりうつくしい詩のことばである。
Copyright © Mi’Te press. All rights reserved.
Designed by MOGRA DESIGN